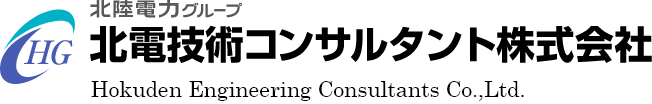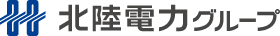宮竹用水第二発電所 実施設計
業務の概要
本発電所の計画及び実施にあたり、当社では、基本設計、実施設計、建築設計、各種申請資料作成支援及び建築工事における施工監理業務を担当しました。
発電計画の概要
本発電所は、最大使用水量6.50m3/sにて水槽(ヘッドタンク)から延長約1,790mの水圧管路で発電所に導き、有効落差11.65mを得て最大580kWの発電を行うもので、年間の供給電力量は約4,036万kWhを計画しています。
宮竹用水第二発電所の発電使用水量は、手取川の白山頭首工から取水した水量のうち、宮竹用水路に最大13.32m2/sを導水し、用水への分水を優先して残りを発電に利用するものであり、発電後は宮竹用水路に還元します。
水車はS形チューブラ水車を採用し、発電機は横軸三相誘導発電機を用いています。


本設計業務における特徴
①既設用水の水量を活用した完全従属型発電
当該発電所は、他の水利使用に完全に従属する発電水利使用の発電所です。完全従属とは、発電のための取水が、かんがい用水のような既存の水利使用の運用に従ってのみ行われるもので、既許可の他の水利使用に完全に従属する水利用の形態を採っているものです。
このような完全従属の水利使用による場合、河川法に基づく水利使用の許可は不要で届出のみになるなど、許認可申請が簡略化されています。
②景観や意識啓蒙に配慮した施設整備
発電所の建築設計にあたっては、地域の景観にも配慮した意匠としたほか、周辺への防音対策も充実したものとしました。
さらに、再生可能エネルギーへの理解と意識啓蒙、子どもたちへの環境学習の活用にも配慮し、水車に水を送る内径2.0mの水圧管路(FRPM管)の展示や、発電所内には発電出力がリアルタイムで表示される電光表示版を設置しています。

③経済性や営農性を考慮した施設設計
本発電所の設計にあたっては、水力発電施設が既存の水田などの営農に影響を与えないよう、用水路脇の管理道路下や市道下に水圧管路を敷設するとともに、施工時にも水田敷地や既設用水路への影響を考慮して立て込み簡易土留による施工を行うなど、周辺への配慮を行いながら施設設計を行いました。
また、管路延長が長くなったり、管路線形に屈曲が多くなったりすると、材料費や施工費の高騰に繋がるため、可能な限り直線性のある線形計画とすることで経済性の向上に配慮しました。


担当者から
農業用水を利用した小水力発電でも、管の内径が2.0m程度まで大きくなるものはこれまであまり無く、施工計画とあいまって設計には苦労がありました。
現在では、本発電所に隣接して手取川宮竹用水土地改良区の社屋が新たに建設され、周辺整備整ってひときわきれいな空間として注目が集まっています。
今回は、発電所の設計から完成まで携わることができ、施工業者さんとも話をして行くことができました。設計上の視点だけではなく、施工性を考慮した設計配慮の重要性が確認できました。施工空間や周囲への影響、施工順序に配慮した設計や、施工時に間違いが発生しにくい配筋設計の必要性など、勉強になりました。
第二土木部 中野 雅樹
お気軽にご相談ください。
お問い合わせフォーム